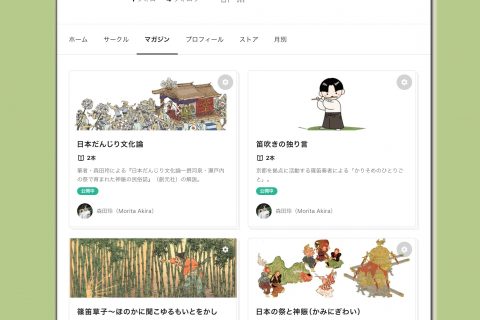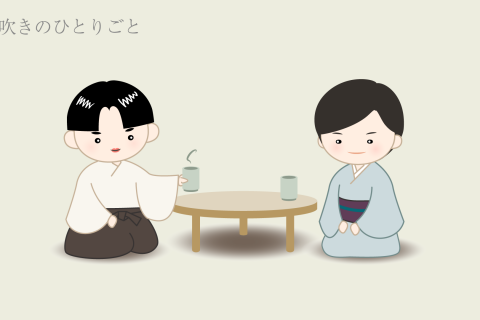2017.04.01
メディア紹介
書評 森田玲『日本の祭と神賑』― 薗田稔先生
弊社代表の森田玲が、折に触れて自身の研究の羅針盤とさせて頂いている、秩父神社の宮司さまで京都大学名誉教授の薗田稔先生から、思いもかけず『日本の祭と神賑』の書評を賜りました。とても丁寧に読み込んで頂いた上での書評であり、下記の書評をお読み頂ければ、本の内容と特徴を具体的に理解して頂けるかと存じます。

<書評> 森田玲著 『日本の祭と神賑(かみにぎわい)』(創元社) → PDF
薗田稔 (京都大学名誉教授・秩父神社宮司)
余談というわけではないが、旧臘十二月一日に日本の国指定重要無形文化財である三十三件の「山・鉾・屋台行事」が一括されて、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界無形文化遺産に登録されることになった。すでに登録済みの「日立風流物」と「京都祇園祭の山鉾行事」に加えて実に十八府県に亘る各地に伝承されている祭礼行事が、正式に世界の文化遺産に認証されたことになる。
一昨年三月に文化庁がユネスコ登録を申請した内容を見ると、「地域社会の安泰や災厄防除を願い、地域の人々が一体となり執り行う『山・鉾・屋台』の巡行を中心とした祭礼行事」となっており、その提案要旨には、「祭に迎える神霊の依り代であり、迎えた神をにぎやかし慰撫する造形物である」山・鉾・屋台は、「伝統的な工芸技術により何世紀にもわたり維持され、地域の自然環境を損なわない材料の利用等の工夫や努力」により持続可能な方法で永く継承され、またその巡行のほか「祭礼に当たり披露される芸能や口承に向けて、地域の人々は年間を通じて準備や練習に取り組んで」いるので、これらの祭礼行事は、「各地域において世代を超えた多くの人々の間の対話と交流を促進し、コミュニティを結びつける重要な役割を果たしている。」と謳われている(平成二十七年三月五日付け文化庁報道発表から)。
本書の書評を前にして直接関係のない時事的内容を紹介するのも、実は本書の内容が、正しくユネスコ登録が成った日本の祭礼行事の提案要旨を個別具体的に詳述している好著であることを、まずは指摘してみたかったからに他ならない。
まず本書の副題に「京都・摂河泉(せっかせん)の祭具から読み解く祈りのかたち」とあるように、現代日本の祭の基本構造を神事と神賑行事から成ると見極めた上で、その神賑行事に登場する神輿・提灯・太鼓台・地車・唐獅子などの祭具を、おもに京都と大阪(摂津・河内・和泉)の各地の祭礼行事の実態に即して取材した成果を詳細に比較検討する手法で、それぞれの起源と歴史的展開を辿りつつ多彩に展開する祭の本質とその魅力を平明に描き出すことに成功している。ともかく本書は、京・大阪の各地に生きる多彩な祭礼行事に取材しながら、それぞれの神賑わいに登場する祭具の象徴分析を通して共有される祭の本質に迫ろうとする着実な論述として読者を惹き付けるものがあろう。
本書の全体構成を紹介すると、まず「まえがき」に続く序章「図説・祭のかたちを読み解く」で豊富な絵図資料を掲載しながら、祭の基本構成と神輿や提灯など、本文各章でとりあげる内容を簡潔に紹介する。第一章「祭の構造」では、時代や地域を超えて共通する祭の基本概念を論じて、祭が「カミ迎え」「カミ祀り」「カミ送り」の三部から成り、また「神事」と「神賑行事」という二つの局面があることを指摘するが、これらは祭の先行研究からしても妥当である。第二章「神輿」では、カミの道行き、つまり一般に神幸祭に登場する神輿の発達史を述べて、特に現在の金飾りは神仏習合の産物だとの指摘は目新しいところ。第三章から第六章までは、「御迎え提灯」「太鼓台」「地車(だんじり)」「唐獅子」の順に、それぞれ豊富な図表と写真を用い多様で魅力的な祭具の世界を紹介しながら、それらが登場する各地の祭礼形態が地域の風土や歴史を反映して多彩だが、それでも互いにさまざまな共通点を見出すことができるとする立論は、着実な事例紹介にも説得力に富んで大いに評価できる。その一例を挙げれば、第三章の「御迎え提灯」では、祭に欠かせない提灯の源流はカミ迎えのための庭燎(にわび)だとの指摘は重要で、この点は、かつて日本民俗学の大成者、柳田國男が古典的名著『日本の祭』(一九四二刊)に、本来の祭では、宵宮に当たる夕べから朝までの間の一夜が大切な部分であって、庭に篝火を焚いて神を迎え、神をおもてなしする方式は、人が最上級の賓客を歓待するに類似だと喝破していることにも通じている。ただし惜しむらくは、なぜ提灯が「祭に欠かせないか」について著者は柳田のように、本来の祭にはカミ迎えに夜間こそが大事であったからこそという指摘に及んでいない点である。現代の祭が、とかく夜の霊性を見失っていることがその理由でもあろう。
さて続く第七章「祭のフィールドワーク」では、著者がこの十年に亘って精力的に採訪した近畿地方一帯の多数の事例を、春夏秋冬の四季に応じた祭礼の類型に即して、しかも著者独自の視点を活かし、豊富なカラー写真や図版を配置して簡潔明瞭に紹介していて、読者も楽しく読み進むことができる。とりわけ祭研究を自認しながら近畿地方の事例に昏い評者には、本書の序章に先立って挿入されている関係社寺の所在地図を参照しながらの貴重な学習であったことを感謝したい。
最終の第八章「祭は誰のものか」こそは、著者がここ十年来の祭を一途に探求するなかで最も本書で読者に訴えたかった「現在の祭が抱える課題」であり、その最たる事例に最近目立つ「祭の土日開催」を採り上げる。著者が彼の幼時から体験的に深く係わってきた岸和田だんじり祭が近年に「土日開催」となって、神事から神賑行事が引き離されたことに衝撃を受け、肝心のカミを忘れて単にヒトの賑わいばかりのイベントと堕してしまうことで、本来の祭が伝承する「人と自然との関わり、森・里・海の連環、カミとヒトとの関係」(あとがき)といった大切な役割を喪失してしまうのではないか、と当面の課題を提起している。
この指摘こそが、本書が日本の祭の本質を衝いた、単なる祭の概説書ではない証しである。
『社叢学研究』第15号(社叢学会 2017.3)
 メディア紹介
『日本だんじり文化論』の取材記事が新聞に掲載
メディア紹介
『日本だんじり文化論』の取材記事が新聞に掲載